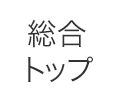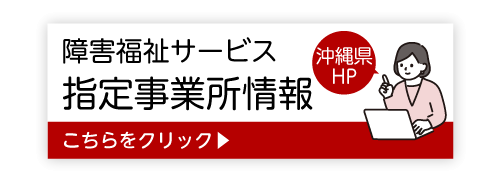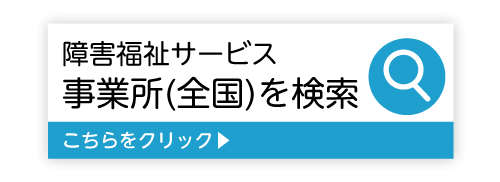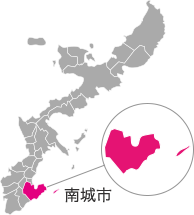各種サービスの給付
障害のある方が受けられる主なサービス
この制度は利用者自らがサービスを選択し、契約により以下のサービスを利用することができます。

ホームヘルパーの派遣
心身の障害のため、日常生活を営むのに支障のある方が、入浴や排泄等の身体介護や、調理、洗濯等の家事援助を行うホームヘルパーを利用することができます。

外出・行動時の支援
心身の障害のため、日常生活を営むのに支障のある方が、入浴や排泄等の身体介護や、調理、洗濯等の家事援助を行うホームヘルパーを利用することができます。

日中における交流や活動の場の提供
地域の事業所などで障害のある方の日中における交流や活動の場を提供し、介護している家族の一時的な休息等の時間を確保します。

短期間の施設への入所
自宅で介護する方の病気、事故、出産、冠婚葬祭等により、心身に障害のある方を家庭で介護することが困難な場合、施設へ短期入所(ショートステイ)することができます。

施設への入所
障害者支援施設へ入所し、必要な介護等を受けられます。※18歳未満の方は児童相談所へご相談ください。

グループホームへの入所
身体的介護の必要性の低い方が、小規模の住宅で共同生活を行い、専門スタッフの介助のもと家事など能力に応じたそれぞれの役割を持ち、家庭に近い環境で生活することができます。

医療が必要な方の看護や介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護等を行います。

身体機能や生活能力向上のための訓練
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労に向けた訓練や一般就労へ向けた支援
働く上で必要な知識の習得や能力向上を目的に、就労の機会や生産活動その他の活動の機会の提供や、一般就労につなげる支援等を行います。▶︎南城市内の就労支援事業所の様子※
※障害の程度によって希望するサービスが利用できない場合があります。
※介護保険サービスを受けることができる方は、介護保険サービスが優先されます。
児童を対象としたサービス
- 児童発達支援
未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。また、医療を必要とする児童(上肢・下肢または体幹機能障害)については、治療等を組み合わせた支援を行います。 - 放課後等デイサービス
就学中の障害児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 - 保育所等訪問支援
保育所等(保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等)を利用する障害児に対し、専門スタッフが保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
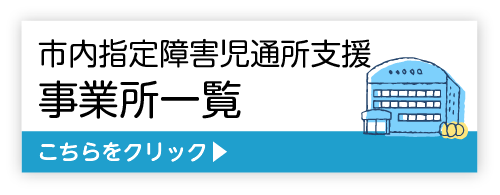
申請からサービス利用までの流れ
- 窓口へ相談(南城市または各相談支援事業所)
「~なことで困っているが・・・」、「どんなサービスが利用できるのか」、「どんなサービスを利用したらよいか」、「どこに施設があるのか」 等 - 相談支援事業所を選定
相談支援事業所では、上記1のような相談をはじめ、市へのサービス申請手続のサポート、サービスを利用するために必要な利用計画の作成、関係機関との調整、サービス利用に関する様々な情報提供等を行います。 - 市へのサービス利用申請
生きがい推進課窓口でサービス利用の申請をします。 - 障害状況の調査
市の調査員が利用者の障害の状況について調査を行います。 - 障害支援区分の決定
調査内容をもとに、専門機関の審査会にてサービスが必要な程度(障害支援区分)が決定されます。 - サービス利用計画案の作成
相談支援事業所は利用者と面談し、障害程度や家庭環境、生活スタイルなど個人にあったサービス利用計画案を作成し、市へ提出ます。 - 支給決定・受給者証の発行
市は障害支援区分やサービス利用計画案等をもとに、サービス支給の可否やサービスを利用できる期間等を決定します。 - サービス利用計画作成
相談支援事業所は、利用者・サービスで利用する事業所等と共に具体的なサービス利用計画を作成します。 - サービス利用開始
サービス利用開始後は一定期間ごとに、相談支援事業所との面談等による利用計画の見直しが行われます。
申請時に必要な書類
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
※手帳以外での申請の場合は、診断書(3ヶ月間有効※精神のみ)や難病、精神通院受給者証等、特別児童扶養手当受給者証等 - 個人番号カードまたは通知カード(マイナンバー)
障害者の場合:本人及び配偶者/障害児の場合:世帯員全員 - 認印(本人、代理人)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の公的証明書)
- 所得課税証明書(市外在住または市外からの転入者のみ)※1
障害者の場合:本人及び配偶者/障害児の場合:世帯員全員分
1~6月に申請する場合:前年1月1日に他市町村在住の方
7~12月に申請する場合:今年1月1日に他市町村在住の方 - 障害年金受給額確認資料(就労継続支援A・B型、施設入所、療養介護の申請時のみ)※1
年金が振り込まれているお通帳、預金出入照会、年金払込通知書 - 下記収入の確認資料(施設入所、療養介護の申請時のみ)※1
・特別児童扶養手当、特別障害者手当(通帳、通知書等)
・工賃(証明書等) - 下記経費の確認資料(施設入所、療養介護の申請時のみ)※1
・社会保険料等(領収書等)
・住民税、所得税、相続税、贈与税、固定資産税(領収書等) - 健康保険証、限度額適用・標準負担限度額認定証(療養介護の申請時のみ)
- 生活保護受給証明書(受給世帯のみ)
※1 対象期間については、事前にお問い合わせください。
利用者負担
サービスにかかる費用の原則1割を利用者が負担します。ただし、利用者負担分については負担上限月額が設けられています。 ※一部サービス対象外の費用もあります。
障害者の利用者負担
| 区分 | 世帯の収入状況※2 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 世帯員全員が市町村民税非課税 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割が16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※2 施設入所(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。
障害児の利用者負担
| 区分 | 世帯の収入状況※ | 負担上限月額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 世帯員全員が市町村民税非課税 | 0円 | |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割28万円未満) | 施設入所以外のサービス | 4,600円 |
| 施設入所の場合 | 9,300円 | ||
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | |
世帯の範囲
| 利用者 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障害のある方(本人)とその配偶者 |
| 18歳未満の障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
住民票上の世帯 |
利用者負担の軽減措置
所得区分によって、下記の軽減措置が受けられる場合があります。
- 施設入所時の食費・光熱水費等の実費負担分への補足給付
- グループホームの利用者への家賃助成
- 医療型障害児入所施設利用時の医療費と食費(18歳未満)の減免
- 児童の発達支援を利用する場合の食費の負担軽減
児童発達支援等の利用者負担の無償化について
3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
| 無料となるサービス |
|
|---|---|
| 対象期間 | 満3歳になって初めての4月1日から3年間 |
留意点
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 上記サービスの無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
(ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。)
高額障害福祉サービス費の世帯単位の軽減措置について
障害福祉サービス、補装具給付、介護保険の利用等で世帯の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
「世帯の基準額」はそれぞれ利用する制度の自己負担上限月額のうち、最も高い額となります。
合算対象の制度
同じ世帯に属する方が、下記制度を2つ以上を利用の場合。
- 障害者・障害児を対象とした各種サービス※
- 補装具
- 介護保険サービス(障害福祉サービス利用者分に限る)
※各制度で利用したサービスの領収書の提出が必要です。
※実質、助成の対象となるのは課税世帯で「所得区分」が一般の場合となります。
※自立支援医療、療養介護医療、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療に係る利用者負担については、合算の対象外となります。
高額障害福祉サービス等給付費 申請時に必要な書類
- 領収書(サービスの利用者負担分)
- 印鑑(申請書押印用)
- 預金通帳等の振込口座番号が確認できるもの(受給者又は合算対象の世帯員のもの)