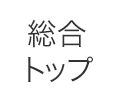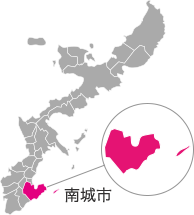国保税の軽減措置について
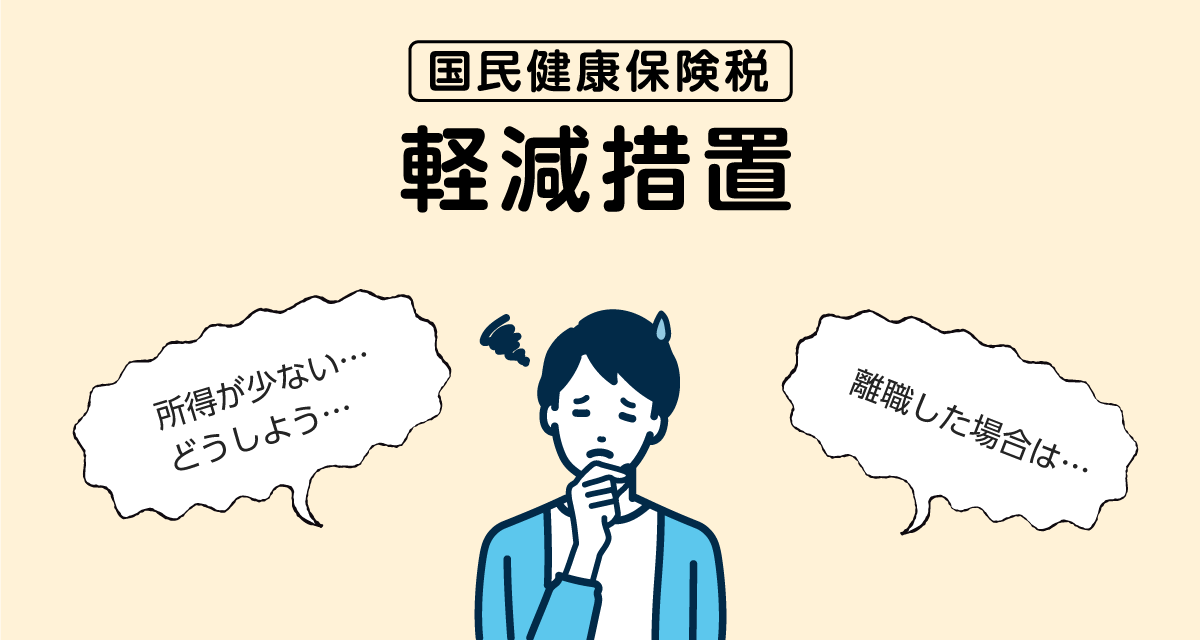
所得の少ない世帯への軽減措置
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者※の総所得金額等の合計が、軽減判定所得基準額以下の場合は、「均等割額」及び「平等割額」が減額されます。この軽減措置は、対象世帯について算定時に適用されるため、申請は不要です。
| 区分 | 基準となる所得金額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(30.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(56.0万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※特定同一世帯所属者とは・・・後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険被保険者資格を喪失した方で、喪失した日以後継続して同一世帯主の世帯に属する方をいいます。軽減判定所得基準額の算出においては、特定同一世帯所属者を含め、軽減判定が行われます。
判定の対象となる所得
- 世帯主(世帯主が国保被保険者でない場合も含む)とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等を合算した金額です。(基礎控除前の金額)
- 65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除します。
- 事業専従者の給与は、事業主の所得とし、専従者の給与はないものとして判定します。
- 長期・短期譲渡所得については、特別控除は適用されません。(特別控除前の金額)
※世帯の中に住民税等の未申告者がいる場合は、所得の把握ができない為、軽減はかかりません。期限内に申告をしましょう。
判定基準日等
判定基準日は4月1日(年度途中からの加入世帯はその加入日)です。判定後、年度途中で加入人数の増減があった場合でも、当初の軽減割合が適用されます。ただし、資格異動届出が遅れたために判定基準日時点の人数に変更があった場合や、判定基準日以降に世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減が再判定されます。
国保税軽減額早見表
未就学児にかかる均等割の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年4月1日から国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の軽減措置を行っています。
| 軽減対象 | 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) ※令和7年度分については、令和元年4月2日以降に生まれた方となります。 (注記)年齢は生まれた日から計算するため、満〇歳に到達する日は誕生日の前日となります。 |
|---|---|
| 軽減内容 | 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。 一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります) なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。 |
未就学児の均等割軽減額
・令和7年度未就学児均等割軽減額
後期高齢者医療制度へ移行に伴う軽減措置
特定世帯等への軽減措置
国民健康保険の被保険者が2人いる世帯で、1人が後期高齢者医療制度へ移行し、もう1人が国保に残った場合の世帯(単身世帯)を「特定世帯」といいます。特定世帯となった月から5年間は「平等割額」2分の1軽減されます。
また、平成25年度税制改正により、5年経過後、さらに3年間は減額割合を4分の1として軽減されます(この世帯を「特定継続世帯」といいます)。この軽減措置は、対象世帯について算定時に適用されるため、申請は不要です。
※後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の資格を喪失した日以後継続して同一の世帯主である必要があります。そのため、世帯主の変更を伴う異動があった場合、軽減措置の対象外となります。
※介護納付金分の「平等割額」には、特定世帯及び特定継続世帯にかかる軽減はありません。
社会保険等で扶養されていた方への減免措置
後期高齢者医療制度の創設に伴い、社会保険等の被保険者であった方が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により下記の内容について減免されます。
減免内容
① 旧被扶養者に係る所得割額を免除
② 旧被扶養者に係る均等割額を下記のとおり減額(5割、7割軽減対象世帯を除く)
| ア 軽減非該当世帯 | 旧被扶養者軽減(5割) | |
|---|---|---|
| イ 2割軽減該当世帯 | 旧被扶養者軽減 (3割) |
2割軽減 |
③ 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額を下記のとおり減額(5割、7割軽減対象世帯を除く)
| ア 軽減非該当世帯 | 旧被扶養者軽減(5割) | |
|---|---|---|
| イ 特定継続世帯軽減該当世帯 | 旧被扶養者軽減(2.5割) | 特定継続世帯軽減(2.5割) |
| ウ 2割軽減該当世帯 | 旧被扶養者軽減(3割) | 2割軽減 |
| エ 特定継続世帯軽減及び2割軽減該当世帯 | 1.5割軽減 | 特定継続世帯軽減(2.5割) |
| 旧被扶養者軽減(1割) | ||
倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方への軽減措置
会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限る)の保険税を軽減する制度です。この軽減措置を受けるためには申請が必要です。
| 制度内容 | 保険税を計算する際に、非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。 |
|---|---|
| 軽減期間 | 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。 ※国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると終了します。 |
| 申請書類 | 国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者用).pdf |
軽減対象者
次の2つに該当する方が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職し、失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証を所持し、離職理由コードが次のいずれかである方
※雇用保険受給資格者証は、雇用保険の失業等給付を受ける方に対しハローワーク(公共職業安定所)より交付されるものです。
※離職理由等についての詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
特定受給資格者
| 離職理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間が3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間が3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者
| 離職理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 23 | 契約期間満了(雇用期間3年未満更新明示無し) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
※離職コードが25(定年退職・移籍出向)、40(自己都合退職)等の場合は、該当しません。
介護保険の適用除外施設に入所された方への免除措置
国保の40歳から64歳の方で、介護保険の適用除外施設に入所された場合、入所期間中の国保税の介護納付金分が免除されます。この免除を受けるためには申請が必要です。
特別な事情のある方への減免措置
災害、その他特別な事情により国保税を納めることが困難な場合は、申請により減免できることがあります。
※事情により納期限内に国保税が納められないときは、分割納付などの納税相談を行っていますので、お早めにご相談ください。
関連ページ