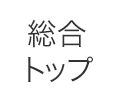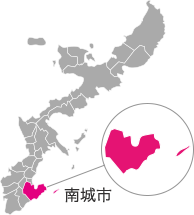予防接種について
予防接種とは
はしかや百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。すべての病気に対してワクチンがつくれるわけではなく、細菌やウイルスなどの性質によってできないものもあります。
予防接種法による予防接種は市町村長(臨時接種は都道府県知事)が行うこととされており、予防接種の対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないとされています。予防接種には、予防接種法に基づく定期接種・臨時接種(公費助成あり)、及び任意の予防接種(接種対象者の保護者の希望により受けるもので自己負担)があります。
予防接種の対象疾患
定期の予防接種
4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)、MR(麻疹(はしか)、風疹(三日はしか))、日本脳炎、結核(BCG)、インフルエンザ(65歳以上)、小児用肺炎球菌感染症、b型インフルエンザ菌(Hib)、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎、ロタウイルス、子宮頸ガン。任意の予防接種
おたふくかぜ、A型肝炎、定期接種で対象年齢外に行うもの海外渡航前に必要な予防接種
黄熱、破傷風、狂犬病、日本脳炎、B型肝炎、A型肝炎予防接種法
<第一条>この法律は、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
予防接種スケジュール
予防接種の間隔
※2020年10月1日より予防接種の間隔が変更になりました。- 熱性けいれん → 6か月間は予防接種を控える(医師から注意をうけた人)
- 風しん・みずぼうそう・おたふくかぜにかかったら→完治後2~4週間あける
- 突発性発疹・手足口病・インフルエンザにかかったら →完治後1~2週間あける
予防接種を受けるときは
予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日頃から保護者の皆さんはお子さんの体質、体調など健康状態によく気を配ってください。そして何か気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけの医師や保健所、市町村担当課にご相談ください。安全に予防接種を受けられるよう、保護者の皆さんは以下を注意の上、当日に予防接種を受けるかどうかご判断ください。
- 送られてきた予防接種の説明書をよく読みましょう。
- 予防接種の間隔やお子さんの健康状態に十分注意して下さい。
- 予診票、母子手帳は必ず持参して下さい。
- 予防接種(DPT-IPV、麻しん・風しん、日本脳炎、BCG、小児用肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(Hib)、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎、ロタウイルス、子宮頸ガン)対象年齢であれば接種できます。予診票を紛失した場合は再発行しますので、健康増進課(917-5324)へご連絡ください。
- 接種の通知が届いた時点で接種済みの場合(前住所地で接種済み)は健康増進課へご連絡下さい。