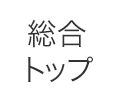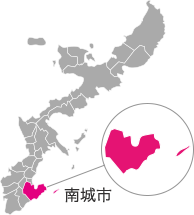令和7年度 南城市施政方針

● はじめに
1. 市政運営の基本姿勢
2. 令和7年度の主要施策について
(1)ひとが育つ
(2)ひとが活きる
(3)くらしの質が高まる
(4)地域が元気になる
(5)まちが整う
3. 令和7年度行財政改革について
4. 令和7年度当初予算について
● むすびに
はじめに
令和7年2月定例会の開会にあたり、市政運営にあたって私の所信の一端を申し述べ、市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
はじめに、令和6年11月の沖縄本島北部豪雨では、大雨の影響で広範囲にわたる被害が発生しました。被災された全ての方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、4月には台湾付近を震源とする地震が発生し、沖縄県に津波警報が発令され、本市においても公共駐車場へ避難者が多く、渋滞が発生し、一時騒然とすることもありました。突発的な激甚災害に対して、日頃から災害に強いまちづくりを目指し、市民の生命と財産を守るため、備えを怠らぬよう、市民の防災意識の醸成に注力し、しっかり取り組んでまいります。
さらに、本市では激甚化、頻発化する災害に備え、日頃から安全迅速に避難できるよう、今年、1月26日には、市民参加による、防災訓練を実施いたしました。
また、2月10日には、市商工会など7団体主催による沖縄県知念半島地域の命と暮らしを守る国道331号バイパスの早期整備を求める住民総決起大会が開催されました。多くの市民の声をしっかりと受け止め、早期整備に向け、引き続き、国に対して強く訴え続けてまいります。
これまでも南部東道路の早期整備に向け、国、県、関係機関等と連携しておりますが、引き続き、早期全線開通に向け取り組んでまいります。
長引く物価高に対しては、これまでに地域経済を回復させるための支援事業をはじめ、市民の負担軽減を図るための施策に取り組んできたところであります。
しかし、依然として生活者の負担は大きく、国においても追加経済対策が表明され、本市においても物価高から市民の生活を守るため、令和6年度に引き続き、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、幼小給食費の半額補助、保育園等についても給食費の値上げに対する支援を実施し、保護者の負担軽減に努めてまいります。中学校につきましては、県において半額補助を実施いたします。
今後も物価の動向は見通せない状況であり、引き続き、国の動向を注視し、きめ細やかな事業展開に努めてまいります。
国民の5人に1人が後期高齢(75歳以上)の超高齢化社会を迎えることで雇用、医療、福祉といった日本経済や社会に深刻な影響を及ぼすとされる、2025年問題、急速に進む少子高齢化社会、本市においても今後起こる問題として、地域コミュニティの維持や活性化、高齢者の社会参加や生涯学習の機会の提供、そして若い世代への負担軽減といった課題が挙げられます。
これらの課題に対応するため、多世代が協力し合う共生社会の実現に向けた取り組みについて検討してまいります。
均衡あるまちづくりは、若者が定住しやすい生活環境の整備が急務であり、いつまでも住み続けたいと思えるまちづくりの実現に向け、力を入れ取り組んでまいります。
これまで進めてきた、大里北小学校跡地については、分譲住宅用地・集合住宅用地、多目的広場などの土地利用が決定しており、引き続き、若者の定住化促進に向けた取り組みを進めてまいります。
令和6年8月24日には、外資系大型商業施設のコストコ沖縄南城倉庫店が沖縄第1号店として開業し、当日は、開店時間を前倒しする程、多くの客が詰めかけておりました。コストコの誘客力を活かし本市の地域資源や地域事業者との連携・共存により、更なる市の発展に結びつけてまいります。
昨年、開催された「南城市まつり」には、多くの市民の皆様にご来場いただき、市の魅力を次世代へと発信する貴重な機会となりました。令和7年度も引き続き開催し、市の魅力をさらに掘り下げ、市民の皆様はもとより、観光客の皆様にも広く発信してまいります。
令和8年1月1日には、4町村が合併し市政20周年の節目を迎えます。
これまで、市民と共に、「人と自然が調和した田園文化都市」づくりを基本理念に長期的な視点で持続可能なまちづくりを進めてまいりました。
引き続き、こどもから高齢者まで全ての世代が健康で夢と生きがいを持ち、笑顔で、誰もが快適に暮らせる、人に優しいまちづくりの実現に力を注いでまいります。
1. 市政運営の基本姿勢
市政運営については、先ほど申し上げた基本理念のもと、「誇りと希望」、「安らぎと生きがい」、「賑わいと活力」に満ちた市民主役のまちづくりを実現するために、公約に掲げた9つの基本政策を進めてまいります。
- コロナ対策を徹底し、市民が健康で活力あるまちづくり
- 人と自然と先端技術が調和した活力あるまちづくり
- 子どもが夢と希望を持ち、可能性を引き出せる教育環境のまちづくり
- 高齢者や障がい者の方が生きがいと安らぎの持てる福祉のまちづくり
- 先端産業集積によるデジタル田園都市のまちづくり
- 農業・漁業・畜産業・ものづくり産業等を支援し、若者に夢と希望が広がるまちづくり
- 歴史と伝統文化を継承し、世界に誇れる平和なまちづくり
- 災害に強い安全安心なまちづくり
- 広域連携による南部広域のまちづくり
これに加え、総合計画に掲げる5つの基本方針に基づき、総合的なまちづくりを推進してまいります。
2. 令和7年度の主要施策について
それでは、総合計画の基本方針に沿って、概要についてご説明いたします。
(1)ひとが育つ
市民の生活水準を高め、市の発展に寄与する人材を育てることを目指し、変わりゆく社会に対応できる環境づくりに努めてまいります。
令和6年度に設置したこども家庭センターにおいては、母子保健機能及び児童福祉機能の連携強化を図り、子育て世帯訪問支援事業等の支援体制及び機能強化に努めてまいります。
また、医療的ケア児や特別な支援を必要とする児童及び保護者に対しては、引き続き、保健、福祉、教育、関係機関が連携し、切れ目ない支援を実施してまいります。
幼児教育センターでは、先進園の園長を招聘した職員研修などを通して、子どもが夢中になる保育環境の充実、幼児教育施設への保育支援訪問を実施し幼児教育の質の向上を図ってまいります。
また、引き続き、スタートカリキュラム期の公開授業や幼児教育施設の公開保育を実施し、幼小中の職員が直接見て語り合い互いの保育・教育についての理解を深めてまいります。さらに架け橋期研修会では、幼保小の職員が架け橋期に大切にしている保育・教育を学び、幼児教育での育ちや学びを小学校以降の学習へつなげることにより、教育の質を高めてまいります。
一人ひとりの能力を最大限に伸長させる特別支援教育の充実に向けて、各学校において、すべての教職員の特別支援教育に関する理解を推進するとともに、学習環境の整備や、学校の支援体制の充実に努めてまいります。
不登校の未然防止や不登校児童生徒の社会的自立に向けた各種施策を展開するため、不登校児童生徒支援体制強化事業を実施し、学校・関係機関と連携し情報共有を図りながら不登校児童生徒が孤立することがないよう支援してまいります。
学校で起きる諸問題を教員だけで解決するには限界があり、子どもの利益を最優先するため、スクールロイヤーの活用を行ってまいります。
スクールロイヤーの活用により、トラブルの際には、初期対応の段階から関わり、いじめの予防教育や、生徒指導に関する法的側面からの助言や指導など、あらゆる学校関係者からの法的相談等に、幅広く対応してまいります。
児童生徒が生まれ育った環境に左右されることなく、安心して学校に通えるよう、各地区にスクールソーシャルワーカーを配置し、関係機関との連携等により、児童生徒や家庭のもつ課題の解決に向けた支援を行ってまいります。
また、モデル地区で導入したスクリーニングについて、一定の成果を踏まえ他地区へ拡大し、支援対象児童生徒の網羅的把握と早期の発見・支援に取り組んでまいります。
放課後の子どもの居場所については、児童館、放課後児童クラブ、放課後子ども教室等に加え、学校やムラヤー等を活用し、子ども達が安全・安心で過ごすための多様な居場所づくりに努めてまいります。
知念地域の小中一貫教育の取り組みは、推進協議会や部会を中心にカリキュラム開発等を進め、地域の実情や特性を活かし、小中学校の学びを連続させ、地域で学び、地域に学び、地域と共に学ぶ教育活動が実現できるように支援してまいります。
GIGAスクール構想により、学校のICT環境は急速に進化しています。引き続き、多くの児童生徒が同時にネットワークに接続できるように、通信環境の整備を進めると共に、中学校の教科書改訂に伴うデジタル教科書の整備も進めてまいります。
また、電子黒板を活用し、タブレット端末やデジタル教科書との連携した「協働的な学び」と「個別最適な学び」の一体的な充実を図ってまいります。さらに、ICT支援員による教員や児童生徒へのサポートを継続し、ICTを活用したわかる授業、魅力ある授業づくりに取り組んでまいります。
「主体的・対話的で深い学び」を創る授業改善を進め、児童生徒一人ひとりが自らの可能性を発揮し、資質や能力を育むことで、確かな学力を育成してまいります。
子どもたちが安心して学ぶことができる教育環境を確保するため、校区内人口が増加し教室が不足している状況にある大里南小学校においては、前年度に引き続き、校舎増築を進め、佐敷小学校においても、同様に教室が不足している状況にあるため、新たに校舎増築を進めてまいります。
環境に配慮した学校づくりのため、前年度に引き続き、市内小中学校照明のLED化を行い、百名小学校においては、空調設備を更新し、快適な教育環境の整備に努めてまいります。
また、市の発展に貢献する人材を輩出することを目的に、意欲ある学生が経済的理由により、高等教育機関への進学を断念することなく、将来へ希望が持てるよう、引き続き、給付型奨学金給付事業等の充実を図り、学習する環境を支援してまいります。
(2)ひとが活きる
近い将来、人口減少や高齢化が進むことが見込まれており、地域の活力維持のための担い手となる人材を積極的に確保する必要があります。その担い手として、地域おこし協力隊制度を活用し、地域課題解決、コミュニティの活性化に取り組んでまいります。
また、ムラヤー構想の実現に資するべく、地域コミュニティの核として、子どもから高齢者まで幅広い世代が集い、活発な地域活動の交流拠点として、ムラヤー(自治公民館)の機能強化整備に取り組んでまいります。地域住民のつながりが深まり、地域全体を支える活動拠点を目指してまいります。
久高島においては、沖縄離島活性化推進事業費補助金を活用して、若者のUIJターンや就業機会の拡大と関係人口の創出を目的に、引き続き、離島体験宿泊交流施設の改修工事を実施すると共に、久高船待合施設及び安座真船待合施設の令和8年度の改修工事に向け実施設計を行ってまいります。
豊富な知識や経験を持つ高齢者の生きがいづくりや就労機会の確保のため、南城市シルバー人材センターの新規会員の加入促進を支援するとともに、センターの将来にわたる安定的経営基盤の確立を目指し、更なる支援強化を図ってまいります。
(3)くらしの質が高まる
地域住民の複雑化・複合化した地域生活課題に対し、包括的な支援体制を整備する重層的支援体制整備事業への移行を推進するため、移行準備事業に取り組んでまいります。
子ども医療費の入院助成については、令和6年度に対象年齢を18歳年度末まで拡充しており、子育て世帯の負担軽減を図るため、制度の継続に努めてまいります。
経済的な問題で生活に困窮している方や、仕事や住まい、家計等さまざまな困りごとや不安を抱えている方の状況に応じた支援を行い、自立促進に向け生活のサポートに努めてまいります。
地域包括支援センターについては、今後の更なる高齢者人口増加に備え、基幹型・地域型包括支援センター及び社会福祉協議会や関係機関・団体等との連携強化を図り、身寄りのない高齢者、認知症や多様な課題を抱えた高齢者の早期把握、早期対応に努めてまいります。
また、身体機能が低下した方へ、リハビリ専門職が、短期集中的に支援を行う、サービス・活動C事業の実施に向けた取り組みも進めてまいります。
高齢者の生きがいづくりでは、元気なうちから住民主体の自主体操サークルや地域ふれあいミニデイサービス、いきいき教室等の介護予防事業への参加を促すなど、地域との繋がりを保ち、住民同士で支え合う仕組みづくりに取り組み、高齢者が孤立せず健康で活動的に生活できるよう支援してまいります。
さらに、健康寿命の延伸及び医療費の適正化に向け、生活習慣病の発症予防及び重症化予防の取り組みについて強化してまいります。
障がい児や障がい者の人格と個性が尊重され、自立した生活や社会参加ができる地域社会を実現させるために、権利擁護の推進に取り組んでまいります。
また、障がいがある人もない人も共に暮らせる社会を実現するために、障がい者差別解消法の趣旨や合理的配慮の普及啓発に取り組んでまいります。
さらに、障がい児や障がい者及びそのご家族等の相談支援体制の強化を図るため、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置に向けて検討してまいります。
災害発生時の避難行動では初動時の「自助・共助」の力が鍵となります。災害時に備えて本人、家族や支援者と災害時の避難経路や避難場所など、避難方法を記載した個別計画書の作成を推進してまいります。
また、避難行動で重要な役割を担う、身近な支え手となる地域と連携し、迅速な支援に繋がるよう避難行動要支援者名簿の提供に関する協定の締結についても引き続き、取り組んでまいります。
災害に強いまちづくりの実現には、共助の精神に基づいた地域間の連携が何よりも重要という観点から、強い地域づくりを促進するため、自主防災組織の設立支援や各区個別の地域防災計画の策定を推進してまいります。併せて、市民の防災意識の醸成にも注力し、防災力の向上に努めてまいります。
また、住民へ情報を瞬時に伝達する、全国瞬時警報システム(Jアラート)について、受信機器の更新作業を行ってまいります。
その一方で、本市は、三方を海に囲まれ海抜の低い地域に多くの市民が暮らしており、災害時における高台への避難ルートの確保が急務となっております。
国道331号知念半島地域における国道バイパスと広域道路ネットワークの一体化整備に向けた取り組みと併せて、南部東道路の早期開通及び南城つきしろインターチェンジから東部地域(低地部)への延伸について、国、県、関係機関等へ要請してまいります。
佐敷海岸においては、現在、県において馬天地区の港整備や新開地区の護岸改修計画が進められており、引き続き、関係機関との連携・協力を図りつつ、背後地と一体となった海辺のまちづくりに取り組んでまいります。
停電対策として、令和2年度に市道知念1号線の電線共同溝が完成し、現在は、電力事業者が各家庭の引き込み工事を進めており、令和7年度は電柱の撤去を予定しています。さらに、国道331号津波古地内も電線共同溝整備道路の指定を受けており、引き続き、事業主体の南部国道事務所と連携して整備完成に向けて取り組んでまいります。
安心で安全に暮らせる環境づくりのため、引き続き、各自治会への防犯灯設置補助を行い、防犯対策に取り組んでまいります。
悲惨な交通事故を減らすため、引き続き、地域、各種団体及び警察と連携して、交通安全活動に取り組み、市民一人ひとりの交通安全意識の向上に努めてまいります。
また、深刻な社会問題となっている、「闇バイト」「振り込め詐欺」などの特殊詐欺被害の未然防止に向けた広報・啓発に努めてまいります。
国指定文化財の整備については、各史跡の整備計画に基づき、糸数城跡保存事業をはじめとした、各史跡の整備や保全に取り組んでまいります。
世界遺産「斎場御嶽」をはじめ、市内に数多く所在する歴史・文化・芸能の発信拠点整備に向け引き続き、取り組んでまいります。
また、市内の複数の公共施設に保管している貴重な収蔵品については、適切な管理のもと次世代に継承していくため、新たな収蔵庫を整備してまいります。
デジタルアーカイブ事業については、地域に根ざした歴史遺産や古写真等のデジタル化による保存を進めるとともに、学校や自治会での活用、定期的な情報発信により観光誘客につなげてまいります。
尚巴志王の三山統一600年に向け、尚巴志王の人となりを知ってもらうため、小学生を対象とした紙芝居を実施してまいります。
(4)地域が元気になる
私たちの地域には、誇れる、美しい自然景観と豊かな歴史文化遺産があります。本市へ訪れた人が、自然景観、歴史文化遺産などの豊かな地域資源や人との交流・体験を通して「幸せ」を感じる感幸(観光)を推進するための取り組みを進めてまいります。その一環として、ウェルネスをテーマとした着地型体験プログラムの造成支援・周知に努めてまいります。
また、民間企業の知見を活用し地域特性を活かした、観光プランの開発や観光交通の推進などに取り組んでまいります。
地域資源を活かし、点から面の観光を推進し、観光を手段として幅広い産業へ受益を広げ、地域社会・地域経済の好循環を図り持続可能な観光まちづくりの実現を図るため、観光地域づくり法人設立に向けた取り組みを進めてまいります。
さらに、観光地としての魅力を高めるため、斎場御嶽周辺、市内県道及び国道沿いの繁茂した樹木の伐採を強化し、良質な景観づくりを創出してまいります。
沖縄南城セレクションで精選された優良な推奨品については、引き続き、市商工会等と連携し、特産品フェアへの出展を行う等、販路拡大・開拓を支援してまいります。
さらに、ふるさと納税制度を活用し、全国へ向け、これからも応援したい地域となれるよう、魅力発信に力を入れ取り組んでまいります。
南城市雇用創出サポートセンターにおいて、市内の求職者、求人企業への支援を労働局と協力連携を図りながら、地域雇用の安定化に向け、さらなる支援に取り組んでまいります。
また、生活困窮者等への就労支援を行うことを目的に、就業する際に有利となる資格の取得に要する費用を補助し、就業の機会を拡大・創出することにより、失業率の改善及び人手不足の解消に取り組んでまいります。
事業経営者の高齢化が進む中、後継者不足問題は深刻化しており、現状を把握するとともに、後継者不足に対するニーズ調査や分析を行い、市商工会、国や県などと連携を図り、必要な支援に取り組んでまいります。
農業振興については、引き続き「なんじょう市民農業大学」を開講し、将来的に持続可能な農業、稼げる農業を目指しながら、本市の農業における課題解決を担える人材を育成してまいります。
また、農業従事者の作業効率化や負担軽減を図るため、農業のデジタル化を推進してまいります。加えて、農地の確保及び有効利用を図るため、沖縄県農地中間管理機構と連携し、出し手の掘り起こしと担い手への集積を行い、耕作放棄地の解消等の農地利活用に取り組んでまいります。
さらなる農業振興に向け、冠水被害の解消などの農用地の保全対策については、農業水路等長寿命化・防災減災事業の愛地寅野原地区、垣花屋宜原地区の実施、知念地区過疎対策事業債を活用した知念安間原地区の農道等補修事業、緊急自然災害防止対策事業債を活用した山里地区の農業水利防災事業の実施に取り組んでまいります。
また、農業生産基盤整備については、県営かんがい排水事業の吉富地区、中山・志堅原地区及び雄樋川2期地区の整備を引き続き、事業主体の県と地元との連携を図り、早期供用開始に向けて取り組んでまいります。
畜産業の振興については、子牛の安定生産と生産乳量の増加を図るため、優良繁殖牛、優良乳用牛の母牛の導入及び保留牛の確保を引き続き推進してまいります。加えて、循環型農業を推進し、糞尿処理の利活用及び飼料費の低減を図ってまいります。
また、経産牛の肥育の支援を行い「なんじょう和牛」のブランド確立に向け、取り組んでまいります。
水産業の振興については、奥武漁港、久高漁港及び志喜屋漁港において、引き続き、環境向上に資する施設整備や水産物の安定供給を図るため、機能保全に取り組んでまいります。
海野漁港背後用地については、引き続き、販売促進に努めてまいります。
(5)まちが整う
平成18年の合併以降、都市計画区域の再編を通じて都市づくりを進めてまいりました。人口は増加に転じ都市構造の形成は着実に進展しましたが、市東部地域の人口は減少傾向にあるなど課題は残されております。こうした都市づくりを取り巻く課題や状況変化に対応するため、令和6年10月に南城市都市計画マスタープランを改定しました。引き続き、市民や地域、事業者・関係団体と協働・共創により、地域全体の活性化とまちの魅力向上等の取り組みを推進してまいります。
将来のまちづくりの根幹である南部東道路については、平成23年度の事業開始から14年が経過しておりますが、これまでの進捗状況から、現在目標とする2020年代後半の全線供用(暫定2車線)開始は全く見通せない状況にあります。引き続き、早期開通に向け、国と県に対し予算確保及び組織体制の強化を要請してまいります。
また、計画的に道路網整備を進め、利便性の高い交通ネットワ-クの形成に取り組んでまいります。
南城市つきしろインターチェンジ南土地区画整理事業については、引き続き、組合と連携を図りながら都市拠点の形成に向けて取り組んでまいります。また、区画整理地内の北側公有地においては、地元の農畜水産物を活用した拠点整備を公民連携により進めてまいります。
市役所庁舎隣接地に、民間事業者の企画力や創意工夫を活かした、多世代が共生できる「まちづくり交流拠点」の整備に向けて官民連携により進めてまいります。
市営住宅については、公営住宅等長寿命化計画に基づき、築年数が経過している百名団地を前年度に引き続き、改修工事を進めてまいります。
Nバス運賃支援事業については、65歳以上及び障がい者手帳を有する市民を対象に、令和5年6月から実証運行しており、昨年度実施した利用者アンケート等から事業効果を検証し、今後の利用促進について、検討してまいります。
また、昨年度に実施した公共交通に関する市民及び学生アンケート結果と新たに取得する人流データを掛け合わせた分析を行うとともに、ワークショップ等を通じて、今後の本市の公共交通について考え、市民参画のもと、南城市地域公共交通計画の策定に取り組みます。
安全安心でバスに乗降できるよう、児童・生徒及び高齢者を対象にバスの乗り方教室や関連イベントを実施し、教育委員会及び各小学校と連携を図り、モビリティ・マネジメント教育を推進してまいります。
「Nバス」及び「おでかけなんじぃ」の運行を継続し、市民や観光客の移動手段の確保に努めるとともに、引き続き、公共交通の利便性向上及び利用促進に力を入れ、持続可能な公共交通の実現を目指してまいります。
玉城総合体育館については、施設利用者の安全確保のために南城市体育施設等再編基本計画に基づき、利用者が安全安心に利用できるよう改修してまいります。
上水道は、住民生活に必要不可欠なライフラインであり、老朽化による事故等が発生した場合、大きな影響を与えることから更新を進めてまいります。着実な更新、水道サービスを持続的かつ安定的に供給するため、水道事業経営戦略の方針に基づき水道使用料の見直しを行う等、健全な経営に努めてまいります。
下水道事業は、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上など生活環境の向上に大きな役割を果たしており、引き続き、流域関連公共下水道区域の大里処理分区については、県と整備方法について協議を行うとともに、市全域の汚水処理区分の再検討を進めてまいります。
また、老朽化が進む下水道施設の機能更新を行うとともに、広域化・共同化計画に沿って集落排水処理施設の統合に向けた取り組みを進め、効率的な施設運営に努めてまいります。
持続可能な下水道サービスのため、下水道への接続を推進するとともに、下水道事業経営戦略の方針に基づき下水道使用料の見直しを行う等、健全な経営に努めてまいります。
デジタル技術を活用した行政サービスの提供を目的に、自治体情報システムの標準化・共通化を推進すると共に、LINE等を活用したオンライン申請の充実、キャッシュレス券売機の導入、マイナンバーカードを活用した市役所窓口のデジタル化を進め、行政手続きの簡素化に取り組みます。
地域社会のデジタル化の指針となる「南城市デジタル田園都市構想」を実現するため、AI技術を通じた水産業におけるスマート漁業や交通分野への活用など、様々な分野における地域課題に向け、デジタル技術を活用した住みよいまちづくりを目指してまいります。
以上が、令和7年度の主要施策の説明となります。ここで申し述べた施策以外の事業についてもさまざまな制度や事業を活用し、市民・自治会・事業者・市などの各主体との協働体制のもと、良好な住環境の形成を図り、将来像である「海と緑と光あふれる南城市」、「住んでよかった、これからも住みたいまちづくり」の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
3. 令和7年度行財政改革について
合併から20年を迎え、その間、絶えず行財政改革に取り組んでまいりましたが、市の財政状況は、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。
社会情勢の変化や多様化・高度化する市民ニーズに対応していくには、市政運営においても変化に適応できる組織力や限られた経営資源を最大限に活かし、業務の効率化と生産性の向上、新たな時代に対応した行政サービスの提供が求められます。
令和7年度より電話交換業務をサポートセンターとして機能強化し、市民課と生活環境課の各種問い合わせや、各種健診の電話対応の集約化を図ってまいります。また、おくやみ手続きの庁内連携を強化し、市民サービスの向上に努めてまいります。
これまでの取り組みを踏まえ、新たな行政改革の方向性を示し、常に経営視点を持ちながら、将来を見据えた堅実で持続可能な行財政運営を目指し、取り組みを継続してまいります。
4. 令和7年度当初予算について
以上、申し上げました政策、施策を実行するため令和7年度当初予算は、
| 一般会計 | 31,788,270 千円 |
|---|---|
| 特別会計 | 6,318,289 千円 |
| 企業会計 | 3,862,364 千円 |
| 総計 | 41,968,923 千円 |
の規模となっております。
歳入では、個人所得や住宅建築等の増加により、市税は増加を見込んでいるものの、歳入総額における自主財源の割合は低く、地方交付税等に大きく依存した財政構造となっております。
歳出では、公債費が減少しているものの、社会保障費や人件費等の義務的経費や普通建設事業費などの投資的経費が増加しております。
令和7年度の主な事業として、玉城総合体育館改修工事、南城市歴史文化発信事業、水産物供給基盤機能保全事業、南城市船越ムラヤー整備事業などを予算計上しております。
予算編成においては、今後も社会保障費の増加が予想され、厳しい行財政運営が見込まれることから、事務事業の取捨選択に取り組み、市民が将来に明るい展望が持てるような施策の展開を図ることを基本に予算を編成いたしました。
むすびに
私の決意は、就任当初から、笑顔輝く活力に溢れた「日本一元気で魅力ある南城市」の実現であります。「共創と連携」を通じて、市民一人ひとりが主役となり、幸せを実感し、市の発展に貢献できる環境を創り上げてまいります。
さらに、日々、新たな課題に挑戦し続け、今の暮らしをより良くするため、市民の皆様と共に歩んでまいります。
市民や議員の皆さまからのご意見を大切にし、各施策の取り組みについて丁寧に説明し、積極的に情報を発信してまいります。
以上が、市政運営に臨む基本姿勢と、所信の一端でございます。
市民の皆さま、議員の皆さまのご理解とご支援、ご協力を心からお願い申し上げ、令和7年度の施政方針といたします。
令和7年2月25日
南城市長 古謝 景春