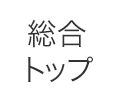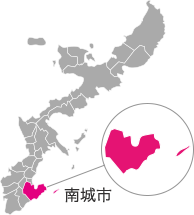市職員向けにハラスメント研修を実施(2025/08/07)
最終更新日:2025年08月08日
南城市役所では、市長をはじめとする幹部職員および管理職員を対象とした「ハラスメント研修」を実施しました。講師として社会保険労務士法人TISが登壇しました。
社会保険労務士法人TISの西里まどか氏
説明を聞く職員たち
今回の研修では、グループワークを中心に、ハラスメントの定義や種類について知るだけでなく、人それぞれの考え方や感覚の違いに気づき、ハラスメントをしない/させない職場づくりについて考えました。
はじめに、TISの西里まどか氏が、ハラスメントの種類やセクハラ・パワハラの三要素について説明し、「ハラスメントは、加害者、被害者、傍観者という三者がいることで発生する」と述べました。そこで実際に、グループ内で三つの役に分かれてロールプレイングを行い、感想を伝え合いました。
発表者からは、「加害者役は話しているうちに興奮してきて、言いすぎてしまう。被害者役は何も言えず、耐えるしかない。傍観者役は“明日は我が身かも”と思い、見て見ぬふりをしてしまう」というリアルな感想があがりました。
これに対し、西里氏からは、「指導者側は言葉選びを意識し、事実のみを指摘すること。受ける側は気持ちを伝える勇気をもち、相談先を知っておくこと。周囲の人は、『まずいな』と感じたら、『休憩しませんか』『大丈夫?』などの声かけをすること」とのアドバイスがありました。
また、ペアで徐々に椅子を近づけていき、人によって適切と感じる距離感が異なることを可視化したワークも行いました。
職員たちは、「ちょっと近いな」「目を合わせるのが難しい」などと、互いの距離感の違いを認識していました。
椅子を動かして距離感を知る
社会保険労務士法人TIS代表の玉城氏
西里氏は、「価値観や考え方、感覚は人それぞれ違うもの。だからこそ適切なコミュニケーションと、職場全体でハラスメントが起きにくい雰囲気づくりが大切」と語りました。
最後に、TIS代表の玉城氏は、「市役所は、カスタマーハラスメントなどの対応もある。相談窓口や対応マニュアルなどを活用してほしい」とまとめました。