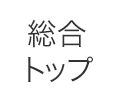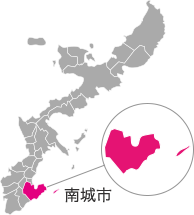子どもに対する性被害・性加害予防を考える研修会を開催(2025/06/17)
最終更新日:2025年06月19日
「こどもに対する性被害、性加害予防を考える」と題した研修会が南城市役所で開催されました。南城市こども支援連絡会と南城市の共催によるこの研修会には、市内の放課後児童クラブのほか、放課後等デイサービスなど障害児通所支援事業所に勤務するスタッフが参加しました。

講師の松川友樹氏(一般社団法人沖縄カウンセリングセンター)

会場は満席に。関心の高さが伺える
講師を務めたのは、一般社団法人沖縄カウンセリングセンターの代表理事であり、臨床心理士の松川友樹氏。松川氏は精神科病院や自治体での心理専門職としての経験を経て、現在は心理支援を中心に幅広い活動を行っています。
今回の研修では、発達障がいのある子どもたちに焦点を当て、性被害と性加害の両面から予防について学びました。
性被害に遭いやすい子どもたちとその背景
松川氏は、発達障がいのある子どもは性被害に遭いやすい傾向があると指摘。「友達づくりが苦手で一人になりやすい」「孤立しやすく、断る力が弱い」などの特性が、被害に巻き込まれるリスクを高める要因になると説明しました。
予防のためには、保護者や支援者とのオープンな関係づくりを土台に、「何がダメなのか」をしっかり伝えること、適切な対人距離やSNSの使い方など、実践的なスキルの習得が重要であると強調しました。
性加害をしないための支援と自己コントロール
一方で、子ども自身が性加害者になることについても重要な課題として取り上げられました。障がい特性により、「相手の気持ちを理解しにくい」「社会のルールを知らない」「性に関する知識が乏しい」といった状況が、結果として加害行為につながってしまうことがあります。
事例として、小学校高学年の男子児童が下級生の女子児童に身体接触を行ったケースを紹介。松川氏は、「いずれ自立していかなければならない。単なる監視ではなく、『自分の選択としてやらない』という自己コントロールの育成が必要」と述べました。
このなかで、短期的な快楽を誘う「報酬系」ではなく、長期的に良い行動を促す「前頭前皮質」を活性化させる必要性を強調しました。
これは「礼儀正しくないと嫌われる」という発想ではなく、「礼儀正しく振る舞う自分がかっこいい」と感じるような、前向きな自己イメージの形成が効果的であるとのこと、プライドや自己肯定感を育てることで、行動の継続性を高めることができると語りました。また、前頭前皮質はストレスに弱いため生活習慣を整え、我慢することを少しずつトレーニングすることも併せて解説しました。
対話と協力で見守る社会へ

研修後半ではグループディスカッションも行われ、参加者同士で性教育の難しさや実践への悩み、取り組みへの意欲などを共有。性教育プログラムの構成例も紹介され、日々の支援に活かせる内容となりました。
最後に、「大人たちはどのように行動すべきか」という参加者の質問に対し、松川氏は「家庭内でオープンに話せる環境を整えること。そして、地域や社会で大人がネットワークをつくり、子どもたちを見守ることが大切」と訴えました。
本研修会は、保護者や支援者一人ひとりが「子どもを性被害・性加害の両面から守る」という共通の課題意識を共有する貴重な機会となりました。