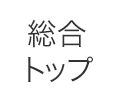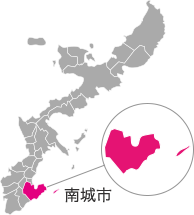安心して地域で暮らし続けるために。「生活支援体制整備事業 第2層協議体」を開催(2025/01/28)
最終更新日:2025年01月30日
地域の支え合いの体制づくりに向けて話し合う「令和6年度 生活支援体制整備事業 第2層協議体」が、市役所1階大会議室で行われました。自治会長、民生委員・児童委員、生活支援コーディネーターなど地域福祉を支える方々が参加し、地域での在り方について意見を交換しました。

地域福祉を支える多く方々が参加
開催に先立ち、南城市社会福祉協議会(社協)の城間寿史会長は、社協が実施主体となっている、コロナ禍で薄くなった住民同士の繋がりを再構築し、地域で互助力を高める『ゆいハート地域づくり事業』の指定地域が増えていることを報告し、「住民主体の福祉活動が広がっていくことを願っています」と、主催者を代表して挨拶しました。

南城市の要介護者の推移を説明

自主体操サークルでの介護予防活動を紹介
今回の協議体は、市生きがい推進課職員による市内の要介護者の推移と介護予防の取り組みの紹介からスタートしました。続いて、理学療法士による市内で広がっている「自主体操サークル」が紹介され、地域互助の介護予防活動への期待が共有されました。さらに、社協の職員による生活支援体制整備事業や協議体(話し合いの場)、ゆいハート地域づくり事業の説明と取り組みも紹介されました。

自治会の垣根を超えて情報交換

話し合いの内容をメモする
最後は、初めての取り組みとして自治会の垣根を超えた情報交換が各テーブルで行われました。参加者は自己紹介がてら公民館でのミニデイサービスの様子を紹介したり、「アパートは増えているが自治会員が増えない」といった悩みなどの情報を共有し、地域での支え合いや、安心して暮らし続けるためにできることを探りました。参加者がそれぞれ話し合いの内容をまとめたメモは、今後の生活支援体制整備事業に活かされます。
生活支援体制整備事業・協議体(話し合いの場)とは
- 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目処に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を目指し、全国の自治体では地域の特性に応じた自主性や主体性に基づいた体制づくりが求められています。
- 南城市でも「地域包括ケアシステム」を目指して、平成29年度から「南城市生活支援体制整備事業」として取り組みを続けていて、生活支援コーディネーターの配置や、地域での協議体(話し合いの場)を実施しています。協議体は第1層(市全体)、第2層(中学校区域圏)、第3層(自治会圏域)に分かれています。
ゆいハート地域づくり事業とは
- 南城市社会福祉協議会が実施主体となり、コロナ禍で薄くなった住民同士の繋がりを再構築し、地域で互助力を高める事業です。各公民館を拠点に「くらしの相談窓口」、「地域支え合い委員会(第3協議体)の支援」、「ハートのまち福祉講座」の3つの内容で展開しています。