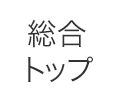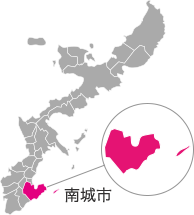南城市の農業と暮らしを再編集する施設とは? トークイベントを開催(2025/01/18)
最終更新日:2025年01月27日

多くの来場者で、関心の高さが伺えます

施設のイメージなどを説明
南城市役所において「南城の農業と暮らしを再編集する」をテーマに、南城市の農畜水産物の振興に向けたトークイベントを開催しました。
このイベントでは、現在計画中の公民連携手法による「農畜水産物利用促進拠点整備事業 - NOLL(ノウル)南城」の説明と、一次産業の可能性や南城らしいライフスタイルをテーマとしたトークセッションが行われました。
第1部 プロジェクトについて

株式会社オガール代表 岡崎正信氏

株式会社ワークヴィジョンズ代表 西村浩氏
まずはじめに、主管部署である公民連携室の職員による南城市の農業の現状説明からスタートしました。南城市では農家戸数や経営面積が年々減少しており、これを打開するための計画が「プロジェクトNOLL南城」です。
この施設はコストコ南城倉庫店の北側に建設される予定で、コストコの集客力を活かしつつ、農業をマーケティング手法と結びつけるとしています。担当職員は「農業は儲かる・楽しいと思える事業にしていきたい」と希望を語りました。
次に、公民連携の「プロジェクトNOLL南城垣花企画委員会」の代表企業をつとめる株式会社オガール代表の岡崎正信氏が事業全体の意義とプランを説明。岡崎氏は「観光の目的の一つは『ローカルな食』。農業が破綻すると沖縄県の観光自体が破綻してしまう。また、南城市誕生以来、農地が宅地に変わり続けているが、農地を守りつつ、儲かる農業を実現することが重要」と課題意識を示しました。
さらに、岡崎氏は「ファーマーズシティー南城」と題した計画について、「ファーマーズマーケットや専門店街、オンラインマーケットの運営に加え、若い農業者が定住できるようヴィレッジ・ワーカーズハウスを整備する。さらに、将来的には長期滞在が可能なレジデンスホテルの建設も視野に入れている」と説明しました。
続いて、施設の設計・デザインを手掛ける株式会社ワークヴィジョンズ代表の西村浩氏が登壇。西村氏は「観光者は、旅行と移住の中間に位置する『暮らすように旅をする』ことを望んでいる」と述べ、施設がビジター(観光者)とローカル(地元住民)の交流を生む場としてラウンジや広場が機能することを目指していると説明しました。
第2部 トークセッション
トークセッションには、岡崎氏、西村氏に加え、農業生産法人株式会社八風畑代表の赤嶺太介氏と、合同会社宮平農園代表の宮平翼氏が登壇しました。
赤嶺氏は廃棄物処理業から農業へ参入した経緯を説明。廃棄物から農業の肥料などを製造し、循環型農業を展開している事例を紹介しました。宮平氏は法人化による安定経営を図り、コーヒーなど多品目栽培や体験プログラムを実施している現状を語りました。
南城市の農業の課題

農業生産法人 株式会社八風畑代表 赤嶺太介氏

合同会社宮平農園代表 宮平翼氏
岡崎氏から南城市の農畜水産業における課題を問われた宮平氏は、「若い農業者が既存のコミュニティに入りきれていない印象がある」と語りました。また、赤嶺氏は生産性を高めるために「集約化や大規模化が必要」と指摘。
これに対し、岡崎氏は「共通しているのは小規模という点。施設内のラウンジをとおしてコミュニティに加わる仕組みができれば、小規模農家も束になって規模を大きくしていけるのでは」と語りました。
事業に対する感想と展望
プロジェクトの感想として赤嶺氏は「農業と加工、販売を結び付けて新しい価値を創造する取り組みで期待している」と述べ、「循環型農業と事業が連携すれば面白い」と語りました。宮平氏は「農家が直接消費者と話せる場を作ることが重要」と提案しました。
西村氏は「農家の話がきける場所として、聖地化するきっかけになれば」と期待を寄せました。また、岡崎氏は「所得向上と規模拡大を通じて南城市の農業の価値を高めたい」と抱負を述べました。
南城市農業の未来
最後に、登壇者たちは南城市の農業に対する展望を語りました。宮平氏は「農業はなくならない。しかし、将来世代は土日は休みたいなどのニーズもある。新しい形での継承が求められる」と語り、赤嶺氏もこれに同調し、「企業としての農業が求められる時代」と述べました。
西村氏は「農家の話を聞く機会はほとんどない。だから食糧危機を実感することがない。農業を真剣に考える機会をつくらないといけないと本当に思う」と強調し、岡崎氏は「農業を振興しなければ、南城市のカルチャー自体が崩壊してしまう。今回のプロジェクトでは大きな役割を持ちながら経営していきたい」と結びました。
南城市の新たな農業振興プロジェクトがどのような未来を切り開いていくのか、引き続き注目が集まります。