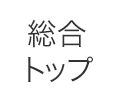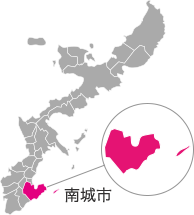発祥の地で「うふざとヌムーチー祭」、ムーチー販売に行列(2024/12/08)
最終更新日:2024年12月11日
南城市大里が発祥とされるムーチー文化の継承と地域の活性化を目的に「うふざとヌムーチー祭」(主催:南城市うふざとヌムーチー祭実行委員会)が大里城趾公園で開催されました。

月桃の甘い香りが立ち込める

蒸しあがった熱々のムーチー
ムーチーは沖縄の方言で「餅」を意味し、月桃の葉で包み蒸した伝統菓子です。その由来は、大里に伝わる鬼退治の伝説に遡ります。首里から大里へ移り住んだ男が鬼と化し、その妹が釘を仕込んだムーチーを使って退治したという逸話が残っています。この話にちなみ、ムーチーは子どもの健康を願い邪気払いとして神仏に供える大切な風習となりました。

ゆっくりと蒸し上がりを待つ

ステージでもイベントを盛り上げる
当日は2500個以上のムーチーが用意され、イベント中に3回に分けて出来立てが販売されました。ムーチーの仕込みには、南城市女性会や農漁村生活研究会、JAおきなわ、南城市商工会の会員らが協力し、月桃の葉の洗浄や蒸し作業を担当しました。初回販売の整理券には予定の1時間前から行列ができ、人気の高さをうかがわせました。

開催前にこの行列!

実行委員会の渡慶次昇委員長
会場内ではムーチーが蒸し上がる際、月桃の甘くスパイシーな香りが広がり、多くの来場者を魅了しました。また、ムーチーづくりの体験ブースも設置され、来場者は手早い包み方や月桃の葉を蒸すコツを教わりながら、自分だけのムーチーを作る楽しさを味わいました。
ムーチーの季節の寒さは「ムーチービーサ」と呼ばれますが、当日も急に気温が下がり冬の訪れを実感する一日となりました。

ムーチーづくり体験

体験で作ったムーチーも実際に蒸します
「うふざとヌムーチー祭」は、かつて旧大里村時代から町村合併当初にかけて行われていた同名のイベントを2016年に復活させたものです。地域活性化を目的に当時の大里地域の区長らが立ち上げたこの祭りは、現在もOBや現役の区長らを中心としたボランティアの手で運営されています。
実行委員会の渡慶次昇委員長は「多くのボランティアの協力のおかげで、伝統を未来に繋ぐことができる。今後は若い世代にも運営に加わってほしい」と語り、祭り継続への意欲を見せました。