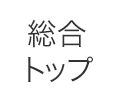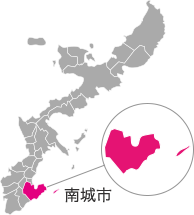津波古自治会で「炊き出し訓練」参加者のアイデア次々と(2024/11/10)
最終更新日:2024年11月12日
津波古公民館で大規模地震を想定した「炊き出し訓練」が津波古自治会主催で実施されました。この訓練は、津波古地区では初の試み。避難所に持ち寄った限られた食材を使い、温かい食事を避難者に提供する体験を通じて、防災意識を高めることを目的としています。

宮城区長から参加者へ想定シナリオの説明

食材からレシピを考える
今回の訓練シナリオは「11月の未明、沖縄本島近海で震度6の地震が発生し、津波古地区の住民が公民館に避難してくる」というもの。訓練の中で提供する温かい食事は、被災者に「生きる勇気を与える」ものであり、津波古自治会の宮城雄一区長も「まずは少人数で課題を見つけることから始めたい」と話します。
持ち寄られた食材を前に、参加者は「何を作るか」話し合いを開始。区長の提案により「すいとん」を汁物として提供することが決定しました。参加者の多くが初めて作る「すいとん」ですが、鯖缶を使って出汁をとり、小麦粉と水の配合を調整しながら進めました。

調理室で具材を切る

屋外では大鍋で調理。すいとん作りに苦戦
また、避難時に活用できる湯煎炊飯法も実践。米をポリ袋に入れて湯煎することで、少ない水で効率的に炊き上げ、洗い物を減らす工夫がされました。さらにおかずには、限られたコンロを有効に使うため、「炒めずにツナ缶で和える」という住民提案の「ソーメンチャンプルー」も登場。住民らの工夫が随所に光りました。

ポリ袋に入れて炊飯

楽しみながらやることも継続するために大切

できあがった料理を配食

完成した3品
ご飯、すいとん、ソーメンチャンプルーが完成すると、参加者全員で試食タイムとなりました。

みんなで「クワッチーサビラ!(いただきます)」

試食後の振り返りも大切
味には満足の声が上がる中、試食後の振り返りでは、次のようなコメントが寄せられました。
- 「皆で知恵を出し合い、初めてのお米の炊き方などを学ぶことができた」
- 「実際に災害時に役立つ経験となった。やったことがあるとないとでは大きな違いが出る」
- 「こうした機会を通じて地域の顔を知ることも重要」
- 「リーダーの役割や役割分担を決めることも必要だと思った」
一方で、「ちょっと豪華すぎたかも。すいとんだけでも十分では」という意見も出され、簡素で現実的なメニュー選びも次回の課題となりました。
宮城雄一区長は、「防災は継続が重要。少人数でも訓練を重ね、意識を高めていきたい」と意欲を示し、特に中学生や高校生の積極的な参加を促す意向を語りました。